オーブンの発酵機能を使ってパンを作るのが初めてでも大丈夫!
この記事では、発酵時間の設定方法や温度調整のコツを分かりやすく解説します。
失敗しないための秘訣や、美味しいパンを作るためのポイントも紹介!
初心者の方も、もっと美味しいパンを作りたい方も、きっと役立つ情報が見つかります。
オーブンを使ったパン作りの時間管理のポイントを、一緒に学んでいきましょう!
オーブンの発酵機能を使ってみよう!基本的な使い方と温度設定

発酵機能とは?
発酵機能の使い方
- オーブンの発酵ボタンを押す
- 温度を30〜35℃に設定する
- 発酵時間を設定する(一次発酵は40分〜1時間、二次発酵は35〜60分程度)
- スタートボタンを押す
発酵機能がないオーブンでは、乾燥を防ぐためと庫内の温度を適温にするために50度程度のお湯を入れた容器を庫内に置き、発酵器の代わりに使うことができます。
発酵機能を使う際は、予熱のタイミングに注意が必要!
二次発酵中に予熱を開始し、過発酵を防ぐことが重要です。
頻繁にパンを作る方は、発酵器がおすすめ。
コンパクトに収納できる発酵器はこちら
発酵機能の温度がたくさんある?!何度に設定すべき?
オーブンの発酵機能には、通常30℃から40℃の間で5℃刻みの温度設定があり、
一般的なパン作りに適した発酵温度は30~35℃程度です。
注意点として、オーブンの発酵機能は必ずしも設定通りの温度にならないことがあるため、40℃付近は少し高すぎる場合があるので、生地の状態を見ながら調整することが重要です。
最適な発酵温度はパンの種類や生地の状態によっても異なるため、レシピや経験に基づいて適切な温度を選択しましょう。
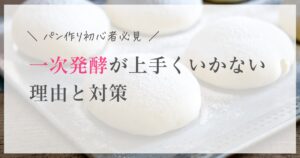
発酵機能付きオーブンの選び方
発酵機能付きオーブンを選ぶ際は、以下のポイントに注目しましょう!
- 温度設定の範囲:30〜45℃で5℃刻みの設定ができるものが一般的です。
- 発酵可能な天板数:MAX2枚程度が多いですが、より多くのパンを一度に発酵させたい場合は、専用の発酵器がおすすめです。
- スチーム機能:ハード系のパンを作る際に便利です。
- 庫内容量:一度に作りたいパンの量に合わせて選択しましょう。
- 設置スペース:コンパクトなモデルもあるので、キッチンのスペースに合わせて選びます。
- 追加機能:スマートフォンアプリ連携やレシピ機能など、使いやすさを向上させる機能も考慮しましょう。
予算と必要な機能のバランスを取りながら、自分のパン作りスタイルに合ったオーブンを選ぶことが大切です。
オーブンの発酵機能を使ったパン作りのコツ

発酵時に生地を入れるボウルのおすすめ
パン作りで失敗しないために大切なのが発酵工程。
その重要な発酵をサポートするボウルの選び方について詳しく解説しますね。
素材で選ぶ発酵用ボウル
ガラスボウル
- 透明性が高く、生地の状態を視覚的に確認しやすい
- 耐熱性に優れ、電子レンジやオーブンでの使用が可能
- 耐熱温度差が120℃以上のものが一般的
- 清潔さを保ちやすく、匂いや色移りの心配が少ない
- 重量があるため、安定性が高い
- 保温性はやや低めで、特に冬場は温度管理に注意が必要
ステンレス製ボウル
- 軽量で扱いやすく、耐久性に優れている
- 熱伝導率が高い
- 衛生的で洗いやすい
- さびにくく、長期間使用可能
- 発酵時の温度管理が比較的容易
- 不透明なため、生地の状態確認には蓋を開ける必要がある
- 保温カバーを併用すると温度維持に効果的
プラスチック製ボウル
- 非常に軽量で扱いやすく、割れる心配がない
- 価格が手頃で、様々なサイズや形状が選べる
- 透明タイプは生地の状態確認が確認しやすい
- 耐熱温度に注意が必要(一般的に70〜80℃程度)
- 傷がつきやすく、長期使用で表面に菌が繁殖する可能性がある
- こまめな洗浄と定期的な交換が望ましい
- 静電気が発生しやすいため、粉類がくっつきやすい場合がある
金属製vs樹脂製 どちらが最適?
オーブンの発酵機能を使用する際、金属製と樹脂製のボウルにはそれぞれ特徴があります。
金属製ボウルは熱伝導性が高く、生地を均一に温めやすいメリットがあります。
また耐久性に優れ、長期間使用できます。
一方、樹脂製ボウルは熱伝導性が低く、生地の温度を安定させやすいです。
軽量で扱いやすく、価格も比較的安価です。
発酵機能付きオーブンではどちらの素材も使用可能なので、選択の際は自分の好みや使用頻度、予算を考慮しましょう。
発酵機能を使う時にラップは必要?
オーブンの発酵機能を使う際、ラップをするかどうかは状況によります。
ラップをする主な理由は、生地の乾燥を防ぎ、表面を滑らかに保つことです。
一方で、スチーム機能付きのオーブンや湿度管理がしっかりしている環境では、ラップをしなくても問題ない場合があります。
また、ハード系パンなど加水率が高い生地では、ラップなしでも乾燥しにくいので、そのままの状態で発酵機能を使用しても大丈夫です。
生地が乾燥すると発酵が進みにくくなるため、ラップをしない場合は濡れ布巾を使用したり、庫内にお湯を入れたコップを置くなどして、湿度を保つ工夫が必要です。
パンの種類やオーブンの機能に応じて適切に選択しましょう!
40度設定での発酵する場合の注意点
オーブンの発酵機能を40度に設定する場合、以下の点に注意が必要です:
- 40度は一般的な温度設定よりも若干高めなので、発酵が早く進む可能性があります。
そのため、生地の状態をこまめに確認しましょう。 - 発酵時間は、レシピの指定より短くなる傾向があります。
過発酵を防ぐため、時間を調整する必要があります。 - オーブンの温度が設定より高くなる場合があります。
必要に応じて途中でオフにしたり、時間を短縮したりして調整しましょう。 - 発酵の見極めが重要です!!
時間だけでなく、生地の状態を観察して判断しましょう!
室温発酵のコツとタイミング
一次発酵
一次発酵は、こねた生地を初めて発酵させる工程です。
室温発酵のコツは、適切な温度と湿度を維持すること!
理想的な環境は、室温25〜35℃、湿度70〜75%です。
生地の乾燥を防ぐため、ボウルにラップをかけましょう。
発酵終了のタイミングは、生地が2〜2.5倍に膨らむまでです。
これには通常40分〜1時間程度かかり、最後はフィンガーチェックでテスト確認をしましょう。
冬場など室温が低い場合は、オーブンの発酵機能を活用したり、暖かい場所に置いたりしましょう。
二次発酵
二次発酵は、成形後に行う2回目の発酵工程。
室温発酵のコツは、一次発酵と同様に適切な温度と湿度を保つことです。
二次発酵の理想的な温度は30〜35℃で、発酵完了のタイミングは、生地が1.5〜2倍に膨らむまで。
通常30分〜1時間程度かかり、生地の側面を軽く押して、ゆっくり戻る程度なら発酵完了のサインです。
二次発酵中も乾燥を防ぐため、ラップや濡れ布巾を使用しましょう。
過発酵に注意が必要で、生地の表面に気泡がたくさん出たり、押すとしぼんでしまったりする場合は過発酵のサインです。
過発酵になると元には戻らないので、こまめに生地の状態を観察してくださいね。
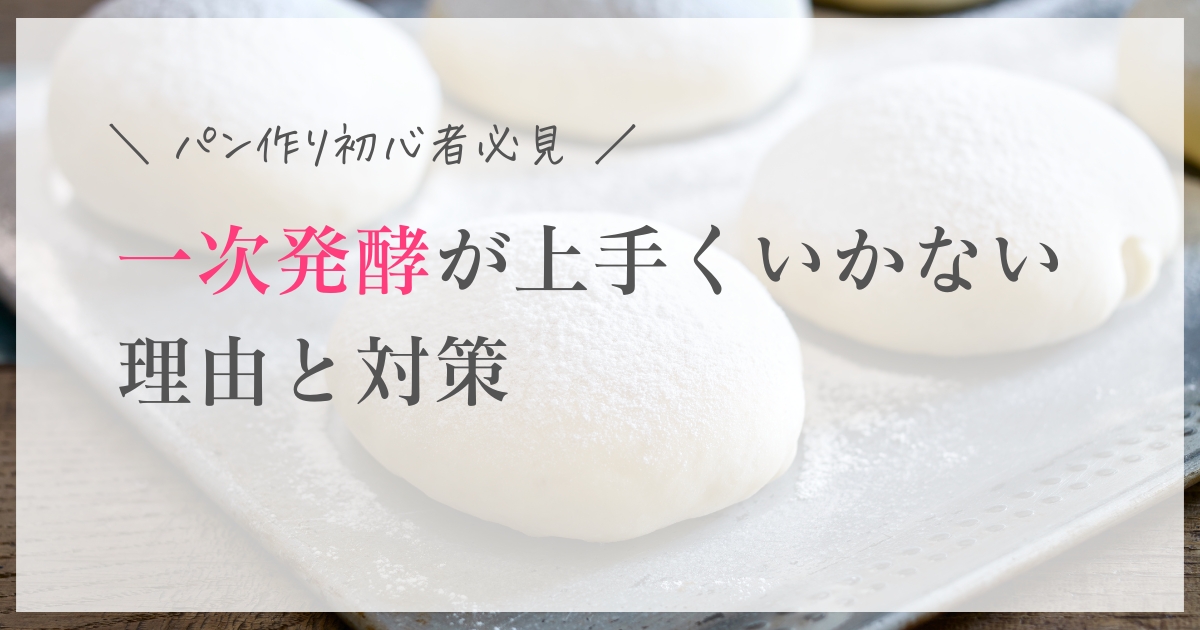
オーブンレンジ発酵機能付きおすすめ一覧!特徴と使い方も

パナソニックのオーブンレンジ:特徴と使い方
パナソニックのオーブンレンジは、多機能性と使いやすさで知られており、特に「ビストロ」シリーズが人気です。
健康的な調理と時短調理をサポートする機能が充実しています。
ビストロシリーズの特徴
- 食材を裏返さず両面を焼くことができる「両面グリル」
- 大容量30Lなのに、業界最小のコンパクト設計
- 価格帯:6〜15万円程度
- フラットな庫内で汚れを落としやすい
- 最高温度300℃の二段オーブン
通常のオーブンレンジシリーズの特徴
- 最高温度250℃の一段オーブン
- 過熱水蒸気調理機能なし
- 価格帯:6万円程度
- 小型でシンプルなモデル
使い方
- 手動調理
温度(70~300℃)や時間を自分で設定して調理します。
パン作りでは予熱後に生地を入れ、適切な温度で焼き上げます。 - 自動調理
「パン」や「スイーツ」などのメニュー番号を選ぶだけで、最適な温度と時間が自動設定されます。 - 発酵機能
30~35℃に設定して一次発酵や二次発酵が可能。庫内に湿度を保つため、水蒸気機能も活用できます。
日立のオーブンレンジ:特徴と使い方
日立のオーブンレンジは、特に「ヘルシーシェフ」シリーズが人気で、健康的な料理をサポートする機能が充実しています。
ヘルシーシェフシリーズの特徴
- 最高温度300℃の二段オーブン
- 予熱が早い:200℃まで約4分50秒
- 100℃以上の過熱水蒸気を使い、油や塩分を落としたヘルシー調理が可能
- 価格帯:4〜10万円程度
- 高機能で大型のモデルが多い
通常のオーブンレンジシリーズの特徴
- 最高温度250℃の一段オーブン
- 過熱水蒸気調理機能なし
- 基本的なオーブンレンジ機能を搭載
- 価格帯:2〜4万円程度
- 小型でシンプルなモデルが多い
使い方
- 手動調理
温度(100~300℃)や時間を自分で設定して調理します。
パン作りでは予熱後に生地を入れ、適切な温度で焼き上げます。 - 自動調理
「パン」や「スイーツ」などのメニュー番号を選ぶだけで、最適な温度と時間が自動設定されます。 - 発酵機能
30~35℃に設定して一次発酵や二次発酵が可能。庫内に湿度を保つため、水蒸気機能も活用できます。
シャープのオーブンレンジ:特徴と使い方
シャープのオーブンレンジは、「ヘルシオ」シリーズが人気で「水で焼く」ウォーターヒート技術が搭載されている
ヘルシオの特徴
- 最高温度300℃の二段オーブン
- 蒸気と温度を組み合わせて、蒸し物から焼き物まで楽しめる
- ハイパワーヒーターで大量の水蒸気を発生させ、余分な脂や塩分を落として必要な栄養素を守る
- 価格帯:8〜15万円程度
- 高機能で大型のモデルが多い
通常のオーブンレンジシリーズの特徴
- 最高温度250℃の一段オーブン
- 過熱水蒸気調理機能あるもの、ないものがある
- 基本的なオーブンレンジ機能を搭載
- 価格帯:3〜5万円程度
- 小型でシンプルなモデルが多い
使い方
- 手動調理
温度(100~300℃)や時間を自分で設定して調理します。
パン作りでは予熱後に生地を入れ、適切な温度で焼き上げます。 - 自動調理
「パン」や「スイーツ」などのメニュー番号を選ぶだけで、最適な温度と時間が自動設定されます。 - 発酵機能
30~35℃に設定して一次発酵や二次発酵が可能。庫内に湿度を保つため、水蒸気機能も活用できます。
東芝のオーブンレンジ:特徴と使い方
東芝のオーブンレンジは、「石窯ドーム」が人気で、パン作り愛好家からの支持率No.1!
石窯ドームの特徴
- 最高温度350℃の二段オーブン
- 丸みを帯びた石窯ドーム構造で、熱風の対流がよくパンやお菓子の二段調理が可能
- 業界最小の奥行き(2024年3月1日現在)
- 価格帯:5〜13万円程度
- 高機能で大型のモデルが多い
通常のオーブンレンジシリーズの特徴
- 最高温度250℃の一段オーブン
- 過熱水蒸気調理機能あり
- 基本的なオーブンレンジ機能を搭載
- 価格帯:3〜5万円程度
- 小型でシンプルなモデルが多い
使い方
- 手動調理
温度(100~350℃)や時間を自分で設定して調理します。
パン作りでは予熱後に生地を入れ、適切な温度で焼き上げます。 - 自動調理
「パン」や「スイーツ」などのメニュー番号を選ぶだけで、最適な温度と時間が自動設定されます。 - 発酵機能
30~35℃に設定して一次発酵や二次発酵が可能。庫内に湿度を保つため、水蒸気機能も活用できます。
オーブン発酵機能の消費電力とは?

発酵機能を使った場合の1回あたりの電気代はどれぐらい?
一般的なオーブンの発酵機能を使った場合の消費電力は30〜40Wだとすると、1時間使用した場合の消費電力量は以下のようになります。
30W × 1時間 = 0.03kWh(最小値)
40W × 1時間 = 0.04kWh(最大値)
日本の平均的な電気料金(1kWhあたり約30円)で計算すると
0.03kWh × 30円 = 0.9円(最小値) 0.04kWh × 30円 = 1.2円(最大値)
つまり、1回1時間の発酵で消費する電気代は約0.9〜1.2円程度ということになります。
ただし、オーブンの種類や設定温度、使用時間によって変わり、最新の省エネタイプのオーブンならもっと電気代を抑えられることもありますよ。
頻繁にパン作りをする人は、月に何回も使うことになるので、年間では数百円の電気代がかかることも。
室温発酵を活用して電気代を節約する方法
室温発酵とは、オーブンの発酵機能を使わず、部屋の温度でパン生地を発酵させる方法です。
この方法を使えば電気代を節約できます。
室温発酵のコツは、生地を保温性の高い容器に入れ、暖かい場所に置くことです。
例えば、ラップをした生地をタオルで包み、暖房の近くやキッチンの暖かい場所に置くと良いでしょう。
夏場は室温だけで十分ですが、冬は発酵に時間がかかります。
また、冷蔵庫で長時間(8〜24時間)発酵させる「低温長時間発酵」という方法もあります。
この方法では冷蔵庫の電気は使いますが、もともと使っている電力なので追加の電気代はほとんどかかりません。
さらに、低温発酵させたパンは風味が良くなるという利点もあります。
よくある質問

まとめ
オーブンの発酵機能は30〜35℃前後で、パン生地を育てる便利な機能です。
発酵機能が付いていないオーブンでも工夫次第で美味しいパンを作ることができるので、ぜひ試してみてくださいね。
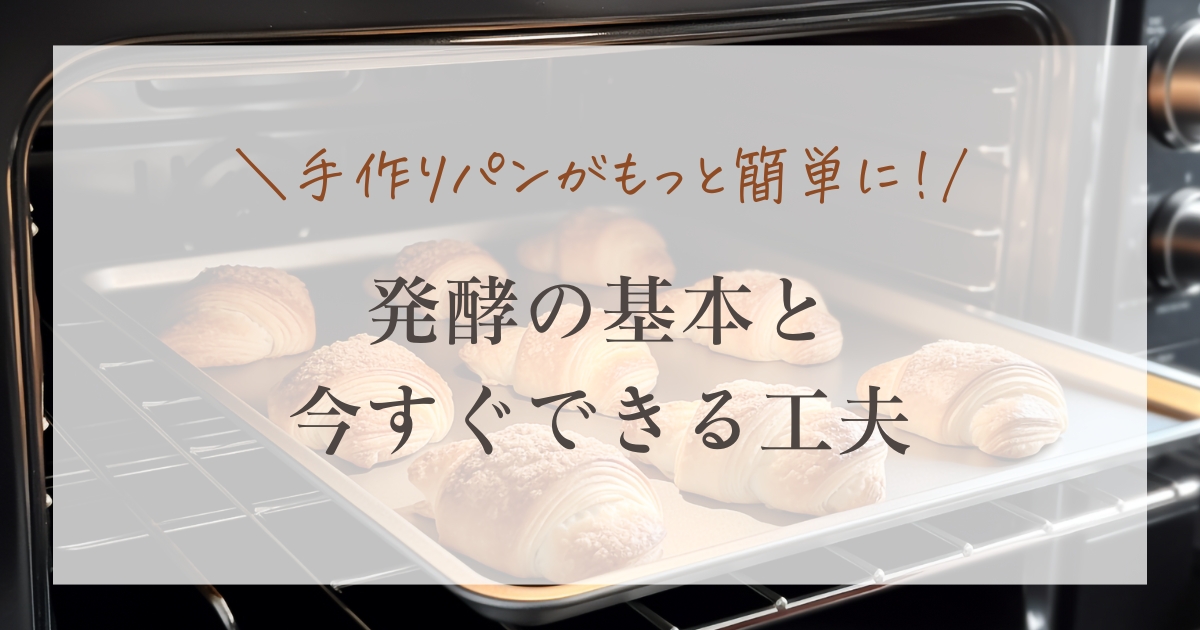
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4679f3c8.fa2ed36f.4679f3c9.f4579573/?me_id=1369889&item_id=10002779&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhitoiro%2Fcabinet%2Fmaker_hario1%2Funi425777.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/28573b21.20b58712.28573b22.54354973/?me_id=1304041&item_id=10317183&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwrappingstore%2Fcabinet%2F087%2F0877%2F087704_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/28573b21.20b58712.28573b22.54354973/?me_id=1304041&item_id=10313448&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwrappingstore%2Fcabinet%2F096%2F0962%2F096255_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4679fafe.ca81628b.4679faff.0f51b1dc/?me_id=1218946&item_id=10161488&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaden-sakura%2Fcabinet%2Fgazou48%2Fne-bs9c-k.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/467a052a.e8fe6154.467a052b.a2eda2f7/?me_id=1347497&item_id=10007146&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftina5750%2Fcabinet%2F05800767%2Fimgrc0124625801.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/28559f1c.c85b8bbf.28559f1d.0a10a7f5/?me_id=1276560&item_id=19784862&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-cutestyle%2Fcabinet%2Fimg048%2Fp000000876489_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/467a0648.87ed3e2d.467a0649.93369d84/?me_id=1363461&item_id=10003864&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsuperdeal%2Fcabinet%2F09061004%2F10450750%2F4974019201238-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/28ba685e.02973022.28ba685f.c8011c64/?me_id=1402701&item_id=10028601&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdenkichiweb%2Fcabinet%2F10709565%2F4904530125836_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/467a0648.87ed3e2d.467a0649.93369d84/?me_id=1363461&item_id=10004970&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsuperdeal%2Fcabinet%2Fyamada%2F2024%2F11188430%2F4904530119941_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)







