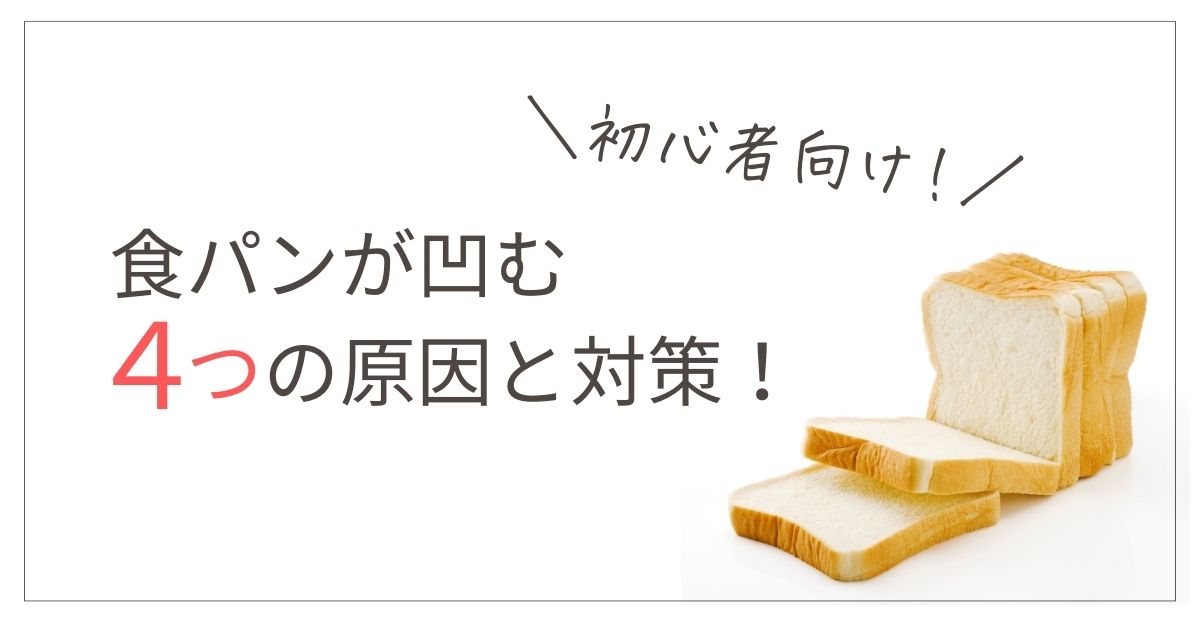せっかく焼いた手作り食パンがへこんでしまう…
そんな「ケービング」現象の原因を4つに分けて詳しく解説!
初心者でも実践しやすい直し方や、ふっくら仕上げるための対策、保存方法のコツまでしっかり紹介します。
食パンがケービング(凹む)する原因は4つ!

こね不足でグルテンが弱い
食パンがへこんでしまう「ケービング」の大きな原因のひとつは、生地のこねが足りないことです。
パン生地は、小麦粉の中のグルテンという成分がしっかりとつながることで、ふっくらとした形になります。
でも、こねが足りないと、このグルテンの力が弱くなり、発酵でできた空気をうまく中にとじこめることができません。
そのまま焼いても、焼き上がったあとにパンの中央がペコッとへこんでしまう「食パン ケービング」が起こりやすくなります。
こねが足りているかを知るには、生地を指でゆっくりのばしてみて、うすい膜のように広がるかをチェックしましょう。
ホームベーカリーを使うときも、こねの時間を確認してみてくださいね!
発酵のタイミングが合っていない(過発酵・発酵不足)
発酵がうまくいかないと、食パンがへこんでしまう「ケービング」の原因になります。
発酵が足りないと生地がふくらまず、逆に発酵しすぎると、生地がふわふわになりすぎて、焼いているときや冷めたときにぺしゃんとつぶれてしまいます。
どちらも「食パン ケービング」が起こるきっかけになるんです。
発酵がちょうどいいかどうかを見るには、「フィンガーテスト」という方法がおすすめ。
生地に指をそっと押してみて、へこみがゆっくり戻るならOK。
すぐ戻ると発酵不足、戻らないと発酵しすぎです。
発酵の時間は、季節や室温でも変わるので、レシピどおりにしても毎回同じにはなりません。
見た目や手ざわりを少しずつ覚えていくと、失敗が減ります。
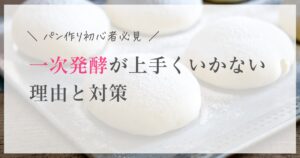
焼成不足やオーブンの温度の問題
食パンをしっかり焼き切れていないと、冷めたときに真ん中がへこんでしまう「ケービング」が起きやすくなります。
見た目は焼けているのに、中まで火が通っていないことが原因です。
特に家庭用オーブンは、表示されている温度と実際の温度に差があることが多いので、予熱が足りないまま生地を入れてしまうと、ちゃんとふくらまずに凹んでしまうことも。
パン作り初心者さんは、必ずオーブンをしっかり温めてから焼き始めましょう。
温度計を使って中の温度を確認するのもおすすめです。
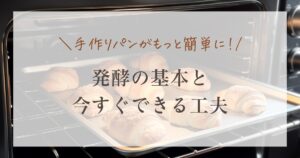
型と材料の比率が合っていない
パンの型に対して、生地の量が合っていないと、食パンがうまくふくらまず、ケービングしてしまうことがあります。
たとえば、型が大きいのに生地が少なすぎると、高さが出ずぺしゃんこに。
逆に生地が多すぎると、焼成中または焼き上がり後に重さで沈むことがあります。
これも「食パン ケービング」の原因になります。
初心者さんは、まずレシピに書かれている型のサイズや粉の量をきちんと守ることが大切です。
型の内側に何ml入るか(=容積)と、どれくらいの粉量が適しているかを知っておくと安心。
最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、ぴったりのバランスをつかめると、毎回ふっくらしたパンが焼けるようになりますよ。
凹んだ食パンの直し方はある?

H3 凹んだ食パンの形は完全に直せる?
一度へこんでしまった食パンを、元のきれいな形に戻すことはむずかしいです。
パンは焼きあがってから冷める間に形が決まるため、真ん中が沈んでしまう「食パン ケービング」は、その時点でほぼ決まってしまっています。
無理に形を整えようとすると、生地がつぶれてしまい、かえって見た目も食感も悪くなります。
残念に感じるかもしれませんが、凹んだままでも中までしっかり焼けていれば、おいしく食べることはできます。
大切なのは、今回の原因をふり返って、次に同じ失敗をくり返さないことです。
次回はふっくら焼けるよう、発酵や焼成を見直してみることをおすすめします。
H3 食感や風味を損なわずにリカバリーするには?
食パンがケービングしてしまっても、食感や風味をおいしく保つ方法はあります。
たとえば、トーストすることで外はカリッと、中はふんわりとした食感が楽しめますし、サンドイッチにすると見た目も気になりません。
焼きたてのうちにラップで軽く包んでおくと、乾燥を防げます。
また、冷めたあとはしっかり密閉して保存すると、おいしさが長持ちします。
すぐに食べきれない場合は、スライスして冷凍保存するのもおすすめです。
ケービングがあっても、少しの工夫で食パンを最後までおいしく食べきることができます。
失敗しても前向きに楽しんでいきましょう。
ケービングを防ぐための5つの対策方法

グルテンをしっかり形成する(こねの見極め)
食パン ケービングを防ぐには、グルテンをしっかり作ることがとても大切です。
グルテンはパンの骨組みのようなもので、生地の中に発酵でできたガスをとじこめる力があります。
こね不足だとその力が弱くなり、焼き上がったあとにパンがつぶれてしまいます。
こねが足りているかを見極めるには、生地を少し取り、ゆっくりのばしてみてください。
うすい膜のように広がればOKです。
ホームベーカリーを使っている場合も、こね時間が短すぎないかチェックすることが大切です。
グルテンがしっかりしていれば、ふっくらとしたパンに仕上がり、ケービングも起こりにくくなります。
こね不足はケービングの原因に!
生地の伸びを確認して、しっかりグルテンを作りましょう。
H3 発酵のタイミングを正しく見極める
食パンがへこむ「ケービング」を防ぐには、発酵のタイミングもとても大切です。
発酵が足りないとふくらまず、焼いてもボリュームが出ません。
一方で、発酵しすぎると生地の力が弱くなり、焼いている途中や冷めたときにしぼんでしまいます。
どちらも食パンがケービングしてしまう原因になります。
初心者さんには「フィンガーテスト」がおすすめです。
指で生地を軽く押して、へこみがゆっくり戻るならちょうどいいサインです。
発酵時間は季節や室温で変わるので、レシピ時間にこだわりすぎず、生地の状態を見ることを意識すると失敗を防げます。
発酵不足や過発酵も凹みの原因。指での押し戻り具合で見極めるのがポイントです。
焼成温度と時間を適切に設定する
オーブンの温度や焼き時間が合っていないと、食パンがしっかり焼けず、冷めたときにへこむケービングが起こります。
特に家庭用オーブンでは、表示されている温度と中の実際の温度に差があることがあるため、予熱が足りないと生地がふくらまずに沈んでしまいます。
温度計を使って予熱が十分にできているか確認すると安心です。
また、焼き時間も短すぎると中まで火が通らず、見た目は良くても後から真ん中がしぼんでしまうことがあります。
レシピ通りに設定しつつ、自分のオーブンのクセも少しずつ把握して、ベストな焼成ができるようにしていきます。
焼き温度が低いと火が通らず沈みます。
しっかり予熱し、適切な時間で焼き切りましょう。
材料の量と型の容積比を合わせる
パンの型に対して生地の量が多すぎたり少なすぎたりすると、焼き上がったときにうまくふくらまず、食パンのケービングが起こってしまいます。
初心者さんは、レシピに書いてある型のサイズと材料の分量をしっかり守ることが大切です。
「型の大きさ(容積)」に対して何グラムの粉を使うか、という考え方を少しずつ覚えると、安定した仕上がりになります。
型にぴったりの生地量を使うことで、焼き上がりもきれいになります。
型と生地量のバランスが悪いと崩れます。
レシピ通りの型と材料で安定した焼き上がりに。

焼き上がり後の冷まし方に注意する
食パンがうまく焼けたと思っても、冷まし方が悪いと、あとからケービングしてしまうことがあります。焼きたてのパンはまだ中がやわらかく、形も不安定なので、取り出すときや置き方によっては生地が凹んでしまいます。焼き上がったらすぐに型から出し、パンを立てるようにしてケーキクーラーなどに置いて冷まします。横に寝かせたままだと、重みでつぶれてしまうこともあるので注意が必要です。また、風通しの良いところで冷ますと、余分な水分がぬけて、べちゃっとせずふんわり仕上がります。焼き上がりの扱いも、ケービング防止にはとても大事なポイントです。
冷ますときの扱いも重要。型から出してすぐ立てて冷まし、凹まない工夫をしましょう。
ホームベーカリーでもできるケービング対策

材料を正確に計量する
ホームベーカリーで食パンを作るときも、材料の計量はとても大切です。
とくに水やイーストの量が多すぎたり少なすぎたりすると、ふくらみに影響が出てしまい、食パン ケービングの原因になります。
計量スプーンではなく、できればスケール(はかり)を使って、1g単位で正確に量るようにしましょう。
おすすめの計りはこちら
パン作りでは、ほんの少しの誤差が仕上がりに大きく影響します。
粉をふるっておくと、より均一に混ざりやすくなります。
手軽なホームベーカリーでも、丁寧な下準備をすることで失敗を防ぎ、おいしい食パンが焼けるようになります。
材料の量が合っていないと失敗の原因に。
1g単位で正確に計量しましょう。
グルテンをしっかり形成するこね工程を選ぶ
ホームベーカリーには、こね時間を調整できるモードや「食パンモード」「ソフトパンモード」などの種類があります。
グルテンをしっかり作るには、しっかりこねてくれるコースを選ぶのがポイントです。
こね不足になると、焼き上がりにパンがへこんでしまう食パン ケービングが起こりやすくなります。
取扱説明書でモードごとの違いを確認し、しっかりこねるモードを選びましょう。
モード選びひとつで、仕上がりが大きく変わってきます。
焼成温度が高めになるモードを選択する
ホームベーカリーの焼成温度は機種によって異なりますが、温度が低すぎると中まで焼き切れず、冷めたときに凹む「食パン ケービング」が起こります。
焼き色が薄い、焼きムラがあると感じたときは、焼成が甘いサインかもしれません。
「焼き色:濃いめ」設定ができる機種であれば、そちらに変更してみましょう。
また、「早焼きモード」は便利ですが、焼きが浅くなりがちなので、初めのうちは標準モードを選ぶのが安心です。
しっかり焼き切ることが、ふっくら食パンへの近道です。
型のサイズと生地量を見直す
ホームベーカリーでも、内釜のサイズと使う粉の量が合っていないと、パンのふくらみに影響します。
粉が多すぎると上に伸びすぎて途中でしぼみやすく、逆に少なすぎると高さが出ず、ふんわりしない仕上がりになります。
機種によって適正な粉の量が決まっているので、取扱説明書や公式レシピの分量を守るようにしましょう。
説明書を見直すだけでも、ケービングの改善につながります。
焼き上がり後の取り出しと冷まし方
焼き上がった食パンは、すぐにホームベーカリーから取り出しましょう。
中に置いたままにすると、蒸気がこもってパンがしぼみやすくなり、ケービングの原因になります。
取り出した後は、パンをケーキクーラーなどに置き、風通しのよい場所で冷まします。
横向きに置いたり、布で包んだままだと、重みや湿気で潰れてしまうことがあります。
焼き上がり後の扱いひとつで、パンの形も食感も大きく変わります。
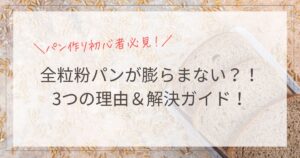
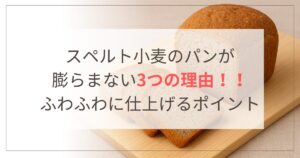
食パンの保存方法|常温・冷凍のベストな使い分け

常温保存のポイントと期間
食パンは焼きたてがいちばんおいしいですが、すぐに食べきれない場合は保存が必要です。
常温で保存する場合は、乾燥とカビを防ぐために、しっかり冷めたあとでポリ袋や保存袋に入れ、涼しい場所に置きます。
保存期間は2日〜長くても3日が目安です。
夏場は特に傷みやすいため、1日以内に食べきれない場合は冷凍するのがおすすめです。
冷凍保存のメリットと手順
冷凍保存は、食パンを長くおいしく保つ方法です。
焼きたてが冷めたら、スライスして1枚ずつラップに包み、冷凍用保存袋に入れて冷凍します。
食べるときは凍ったままトーストすればOK。
焼きたてのような香ばしさが楽しめます。
冷凍なら約2週間〜1ヶ月保存できます。
まとめて焼いた食パンをムダなく使い切るのにぴったりです。
保存方法で変わる美味しい食べ方
保存方法によって、食べるときの食感や味わいが変わります。
常温保存のパンは軽くトーストして外をカリッと、中をふわっと仕上げるのがおすすめです。
冷凍パンは凍ったまま焼くと、焼きたてに近いおいしさがよみがえります。
保存前にスライスしておくと、食べたいときに手軽に使えて便利です。
保存も工夫次第でおいしさが続きます。
FAQ|食パン作りのよくある質問

まとめ
手作り食パンがへこんでしまう「ケービング」は、こね不足や発酵の失敗、焼き温度の不備など、いくつかの原因が重なって起こります。
ですが、その一つひとつを丁寧に見直すことで、ふっくらとしたおいしい食パンが焼けるようになります。
特に初心者さんは、「ちゃんとできたかどうか」よりも「次はどうすればいいか」に目を向けてみましょう。
パン作りは繰り返すほどに上達していきます。
今回ご紹介したケービングの対策を少しずつ取り入れながら、失敗も経験に変えて、自分なりのベストなレシピを見つけていってくださいね。