
こんにちは、現役パン教室講師/教室運営コンサルタントのyuiko です。
イースト臭が苦手という自分の体質から、微量イースト&国産小麦を使ったオーバーナイト製法のパン作りにたどり着きました。
現在は、素材の良さを活かしたパン作りを伝えるオーバーナイト専門のパン教室を主宰しています。
また、cottaパートナーとしても活動中。
パン作りを始めたばかりの頃、レシピに書かれている「ドライイースト」と「インスタントドライイースト」の違いに戸惑ったことはありませんか?
名前は似ていても、実は使い方や特性がちょっと違うんです。
「どっちを使えばいいの?」
「うちにあるのはインスタントだけど、普通のドライイーストのレシピでも使える?」
そんな疑問をスッキリ解決するために、今回はドライイーストとインスタントドライイーストの違い、それぞれの使い方と、置き換え方法をわかりやすく解説していきます。
知らずに使うと、発酵がうまくいかない原因にもなりかねません。
初心者さんでも迷わず選べるようになるので、ぜひ最後までチェックしてくださいね!
ドライイーストとインスタントドライイーストの違いは?


ドライイーストとは?
ドライイーストは、水で戻してから使うタイプのイースト菌です。
粉末状ですが、発酵力を安定させるために、最初にぬるま湯でふやかす「予備発酵」が必要になります。
最近ではこのタイプを見かける機会が減ってきましたが、昔ながらの製パンレシピや製パン学校では、今も使われています。
やや扱いにくさがあるため、初心者には少しハードルが高め。
ただし、発酵のコントロールがしやすいという特徴があり、パン作りに慣れてきた方や、風味にこだわりたい人には根強い人気があります。
本格派のパンを目指したい人には、一度は使ってみる価値があるイーストです。
インスタントドライイーストとは?
インスタントドライイーストは、予備発酵が不要で、粉に直接混ぜて使えるタイプのイーストです。
家庭用レシピでは、いまやこちらが主流。
粒が細かく、水に溶けやすく加工されているので、発酵にかかる時間も短く、時短調理にもぴったりです。
失敗が少なく扱いやすいため、初心者にも最適なイーストといえます。
また、冷凍生地に対応している製品もあり、パン作りの幅が広がるのも魅力のひとつ。
ちなみに、レシピに「ドライイースト」とだけ書かれている場合は、実際にはこのインスタントタイプを指していることが多いです。
パン作りを始めたばかりの方には、まずこのインスタントタイプから使ってみるのが安心です。
セミドライイーストとは?
セミドライイーストは、水分を少し含んだ中間タイプのイーストです。
見た目はややしっとりしていて、完全な乾燥ではないため、冷蔵保存が必要になります。
風味が良いとされ、ハード系のパンやフランスパンなど、香りを重視するパンに向いていると言われています。
ただし、日本ではあまり流通しておらず、入手しづらいのが現状。
保存方法も少し面倒で、家庭で扱うには不向きな面もあります。
パン教室やプロの現場など、こだわりたい人向けのイーストと考えておくとよいでしょう。
初心者さんが無理に選ぶ必要はありません。
まずは使いやすいインスタントタイプで十分です。



私はセミドライイーストを使用しています。
赤サフと金サフの違いとは?
まず、赤サフはスタンダードタイプ。
クセがなく、幅広い種類のパンに使える万能型で、家庭用レシピでもよく使われています。
そのまま粉に混ぜるだけで使えるので、初心者でも扱いやすい定番商品です。
一方、金サフは「高糖生地専用タイプ」。
ブリオッシュや菓子パンのように、砂糖が多い生地でもしっかり発酵してくれる強さを持っています。
赤サフでは発酵が遅れがちな甘いパンも、金サフなら安心。
つまり、
赤サフ=基本用/万能タイプ
金サフ=甘いパン専用/高糖耐性タイプ
レシピやパンの種類に合わせて、上手に使い分けることがポイントです。
赤サフはこちら↓
小分けになっているものが使い勝手が良くてお勧め!
金サフはこちら↓
生イーストとは?
生イーストは、水分をたっぷり含んだ“生きた状態”のイーストです。
パン屋さんや製パン工場など、プロの現場で使われることが多いタイプ。
見た目はクリーム色のペースト状で、扱いには冷蔵または冷凍保存が必須。
保存期間も短く、とてもデリケートなイーストです。
発酵力が強く、風味も豊かなので、本格的なパン作りにはぴったり。
ただし、扱いが難しく、計量や温度管理のコツが必要なため、家庭用にはあまり向いていません。
また、市販のスーパーではまず手に入らず、製パン材料店や業務用ルートでの入手が必要。
あえて挑戦してみたい方以外は、まずインスタントタイプから始めるのが無難です。
どのイーストを選ぶべき?比較表でチェック
| 種類 | 特徴 | 初心者向き | 保存方法 |
|---|---|---|---|
| ドライイースト | 予備発行が必要 | △ | 常温/開封後は冷蔵 |
| インスタント | そのまま使用可能 | ◎ | 常温/開封後は冷蔵 |
| セミドライ | そのまま使用可能/冷蔵保存が必要 | △ | 冷蔵必須 |
| 赤サフ(インスタント) | 万能タイプ | ◎ | 常温/開封後は冷蔵 |
| 金サフ(インスタント) | 糖分が多いパンに使用 | ◎ | 常温/開封後は冷蔵 |
| 生イースト | 発酵力が強いがプロ向け | × | 冷蔵必須 |
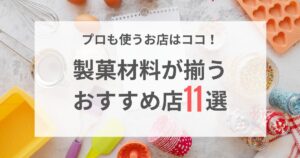
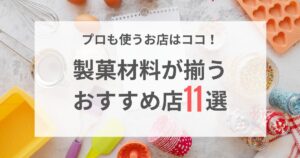
ドライイーストとインスタントドライイーストの置き換えや代用は?


インスタントをドライイーストに置き換える場合
レシピに「インスタントドライイースト」と書かれているけれど、手元には「ドライイースト」しかない。
そんなときは、量と使い方の調整が必要です。
まず、インスタントに比べてドライイーストは発酵力がやや弱めなので、置き換えるときは1.25倍の量が目安。
たとえば、レシピにインスタント3gと書かれていたら、ドライイーストは約3.75g使います。
さらに大切なのは、必ずぬるま湯で予備発酵をしてから使うこと。
水温は約35〜40℃が目安。熱すぎるとイーストが死んでしまうので注意です。
手間は少しかかりますが、丁寧に戻せばドライイーストでも十分代用可能。
時間に余裕のあるときや、風味を重視したいときには試してみる価値があります。
ドライイーストとインスタントドライイーストの代用は?
基本的に、ドライイーストとインスタントドライイーストはお互いに代用可能です。
ただし、量と使い方を正しく調整することが大前提。
● ドライイースト → インスタントに代用する場合
→ 量を80%に減らす。
予備発酵は不要で、そのまま粉に混ぜてOK。
● インスタント → ドライイーストに代用する場合
→ 1.25倍の量に増やす。
必ずぬるま湯で予備発酵をしてから使う。
また、レシピによっては発酵時間や膨らみ方が微妙に変わることもあります。
特に、低温長時間発酵や冷蔵発酵をする場合は、イーストの種類に応じて調整が必要になるケースも。
家庭用で楽しむ範囲なら、代用しても大きな問題は起きにくいですが、本番用のパンや販売品などでは慎重に扱いましょう。
置き換えに失敗しないための注意点
イーストの置き換えは可能ですが、ちょっとしたことで発酵に失敗するリスクもあります。
ここでは、特に注意しておきたいポイントをまとめます。
まず、量の換算ミスに注意。
ドライイーストをインスタントに代えるときは80%に減らす。
逆にインスタントをドライイーストに代えるときは1.25倍に増やす。
この比率を間違えると、膨らみすぎたり、逆に発酵不足になったりします。
次に、予備発酵の有無をしっかり把握しておくこと。
ドライイーストは必ずぬるま湯で戻す。
この工程を省くと、イーストが十分に働かず、パンが重たい仕上がりになることも。
さらに、水温にも要注意。
60℃を超えるとイーストが死んでしまうため、35〜38℃のぬるま湯を使うのが安全です。
最後に、イーストの鮮度も重要なポイント。
封を開けたら、しっかり密封して冷暗所に保管しましょう。
劣化したイーストは、いくら正しい分量でも思ったように膨らまない原因になります。
インスタントドライイーストはスーパーで買える?


スーパーで買える
インスタントドライイーストは、ほとんどのスーパーで市販されています。
とくに製菓材料コーナーや、強力粉・薄力粉の近くに並んでいることが多いです。
日本のスーパーでよく見かけるのは、日清や昭和産業、カメリア(日本製粉)などの国産ブランド。
少量の個包装タイプ(3g×6袋など)もあるため、パン作り初心者にも使いやすく、無駄なく使い切れるのが魅力です。
ただし、店舗によっては取り扱いがないこともあるので、確実に手に入れたい場合はネット購入もおすすめです。
スーパーで見かけるイーストはこのタイプ
ネットで買える
インスタントドライイーストは、ネット通販でも簡単に購入可能です。
Amazon、楽天、Yahooショッピングなどの大手ECサイトはもちろん、富澤商店やcotta、ママパンなどの製菓材料専門店もおすすめ。
ネットで買えば、業務用サイズ(500g〜)や赤サフ・金サフなどの海外ブランドも手に入りやすいのがメリットです。
また、スーパーでは見かけない種類や、有機イースト、グルテンフリー対応の商品も選べます。
価格も比較しやすく、まとめ買いで割安になることもあるため、定期的にパンを焼く人にはネット購入のほうが便利です。
スーパーで買うときの選び方のコツ
スーパーでインスタントドライイーストを選ぶときは、まず「予備発酵不要」と書かれているかチェック。
インスタントタイプであれば、粉に直接混ぜて使える=失敗しにくいです。
次に、小分けパックかどうかも大事なポイント。
一度に使う量はほんの数グラムなので、開封後の劣化を防ぐには個包装タイプがおすすめ。
パッケージに「食パン用」「菓子パン用」と書かれているものもあるので、作りたいパンに合ったものを選ぶと安心です。
特に菓子パンを作るなら、「金サフ」など糖分に強いタイプを選ぶと発酵が安定します。
迷ったら、国産メーカーで“インスタントドライイースト”と明記されている商品を選べばOKです。
買ったインスタントドライイーストの保存方法と注意点
インスタントドライイーストは、湿気と熱に弱いため、保存方法に注意が必要です。
未開封であれば、常温保存でもOKですが、開封後は冷蔵庫で保存するのがベスト。
特に500gなどの大容量タイプを使う場合は、しっかり密閉容器に入れて、乾燥剤を入れると劣化防止に効果的。
スプーンを使うときも、湿気や水分が入らないよう、乾いたものを使うことが大切です。
また、開封後はなるべく早めに使い切るのが理想。
使用期限が切れていなくても、保存状態が悪いと発酵力が落ちてしまうことがあるので注意しましょう。
冷凍保存も可能ですが、結露しやすくなるため、出し入れ時は手早く扱うことがポイントです。


インスタントドライイーストのおすすめはどれ?


初心者におすすめのインスタントドライイースト3選
パン作りを始めたばかりの方にとって、どのイーストを選べばいいか迷うのは当然のこと。
そこで、初心者さんでも失敗しにくく、扱いやすいおすすめのインスタントドライイーストを3つご紹介します。
- 赤サフ(サフ インスタントドライイースト 赤)
万能タイプで、食パンから菓子パンまで幅広く対応。
粉にそのまま混ぜるだけでOK。とにかく使いやすい。 - カメリア(日本製粉)インスタントドライイースト
スーパーでも手に入りやすく、価格もお手頃。
個包装タイプもあり、初めてでも扱いやすい国産商品。 - サフ金(サフ インスタントドライイースト 金)
少し慣れてきたらおすすめ。
糖分の多い菓子パンやブリオッシュ系に強い発酵力を発揮します。
最初の1袋は、赤サフかカメリアを選べばまず間違いなし。
迷ったら、まずは小容量で試してみましょう。
赤サフはなぜプロにも人気なのか?
パン職人からも家庭のパン好きからも支持され続けているのが、「赤サフ」です。
このイーストがプロにも選ばれる理由は、安定感と汎用性の高さにあります。
赤サフは、気温や湿度の変化に強く、発酵力が安定しているのが大きな強み。
どんなレシピにも合わせやすく、ハード系からソフト系まで幅広く使える万能選手です。
また、粒子が細かくて水にもよくなじみ、予備発酵不要で時短にもなる。
焼き上がりの香りや膨らみも安定しており、仕上がりに差が出やすいプロの現場でも信頼されているのです。
つまり、初心者でもプロでも、迷ったら赤サフでOKということ。
それほどまでに、完成度の高いインスタントドライイーストです。
国産派に人気のインスタントドライイースト
「やっぱり国産が安心」という方には、カメリア(日本製粉)や日清製粉のインスタントドライイーストがおすすめです。
スーパーでもよく見かける身近な商品ですが、品質はしっかりしており、家庭用にぴったり。
とくにカメリアは、パンの香りと膨らみのバランスが良く、クセが少ないのが特徴。
個包装タイプも販売されていて、使い切りしやすく、保存管理がラクなのもポイントです。
また、国産イーストは日本の小麦との相性も良く、安定した焼き上がりが得られやすいという声もあります。
小ロットで試せるのも魅力のひとつ。
「はじめてパンを焼くからこそ、手軽に・安心して使いたい」
そんな方には、国産のインスタントドライイーストがお勧めです。
自分に合ったイーストの選び方
イーストの種類が多すぎて決められないと感じたら、「自分がどんなパンをよく焼くか」を基準に選びましょう。
- 毎日食べるシンプルなパン(食パン・丸パンなど)なら赤サフやカメリア
- ふわふわ甘いパン(あんパン・ブリオッシュ)なら金サフ
- ハード系やこだわりパンが多いならセミドライや生イーストに挑戦
また、使用頻度が高い方は、500gなどの大容量パックでコスパ重視。
たまにしか作らない方は、個包装タイプで無駄を防ぐのがベストです。
さらに、保管環境(冷蔵・冷凍の可否)や、入手しやすさも考慮しましょう。
無理なく使い切れるサイズ&頻度で選ぶことが、失敗しないコツです。


パン作りでの使い方の違い


予備発酵(事前にぬるま湯で溶かす必要はある?)
イーストには種類によって、「そのまま使えるもの」と「ぬるま湯で溶かす必要があるもの」があります。
まず、インスタントドライイーストは予備発酵不要。
つまり、粉と一緒にそのまま混ぜてOKです。
初心者に人気の理由は、ここにあります。
一方で、ドライイースト(予備発酵が必要なタイプ)は、使う前にぬるま湯でふやかす工程が必要です。
この手間を省いてしまうと、発酵がうまく進まなかったり、パンが膨らまない原因になります。
使用するイーストの袋や説明書きに、「予備発酵不要」「そのまま使える」などの表記があるか必ず確認しましょう。
加えるタイミングの違い
インスタントドライイーストは、粉や砂糖・塩などの材料と一緒に最初から混ぜて使うことができます。
そのため、計量さえできれば、誰でも手軽に使えるのがメリットです。
一方で、予備発酵が必要なドライイーストは、最初に水でふやかして“活性化”させてから生地に加える必要があります。
そのまま粉に混ぜると、イーストが十分に働かず、発酵不良になることも。
また、生イーストやセミドライイーストを使う場合も、生地に加える順番や混ぜ方にコツが必要です。
「どの段階で加えるか」を間違えると、パンの仕上がりに大きく影響するため、
イーストごとの基本の使い方はしっかり確認してから作業することが大切です。
発酵時間に与える影響
イーストの種類によって、発酵にかかる時間や膨らみ方に違いがあります。
たとえば、インスタントドライイーストは発酵力が強く、短時間で膨らみやすいのが特徴。
時短レシピや、サクッと作りたい日にはぴったりです。
一方、ドライイーストや生イーストは、発酵に少し時間がかかる傾向があります。
その分、じっくり時間をかけることで風味が豊かに仕上がるともいえます。
また、同じインスタントタイプでも、金サフ(高糖耐性)は甘い生地に強く、菓子パンでもしっかり発酵。
赤サフはオールマイティに使えますが、糖分が多すぎるとやや発酵に時間がかかることも。
レシピ通りに作っても、使うイーストの種類が違えば「膨らみすぎる」「膨らまない」と感じる原因になります。
発酵の進み具合は、生地の状態を見ながら調整するのがいちばんのコツです。
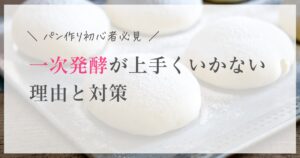
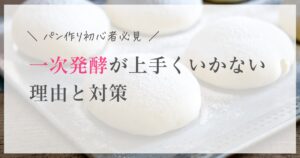
よくある質問(FAQ)


まとめ
パン作りに欠かせないイースト。
でも、「ドライイースト」「インスタント」「赤サフ?金サフ?」「生イーストってなに?」など、はじめは戸惑うことばかりですよね。
まず初心者に一番おすすめなのは、インスタントドライイーストです。
粉にそのまま混ぜて使えるので失敗しにくく、スーパーでも手軽に手に入ります。
とくに赤サフや国産のカメリアは、扱いやすく人気があります。
一方で、ドライイースト(予備発酵が必要なタイプ)や、風味の良い生イーストは、少し慣れてきた中級者以上におすすめ。
発酵力や風味の面で優れていますが、保存や使い方にコツがいります。
また、金サフは甘いパンに強い高糖耐性タイプ。
菓子パンやブリオッシュをよく作る方にはこちらがぴったりです。
代用も可能ですが、インスタントとドライイーストでは使用量や使い方に違いがあるので、置き換えるときは注意が必要です。
基本の目安は、「インスタント→ドライイースト=1.25倍」「ドライイースト→インスタント=80%」。
さらに、ドライイーストはぬるま湯での予備発酵が必須なので、忘れずに行いましょう。
保存方法も重要なポイントです。
未開封なら常温でもOKですが、開封後は冷蔵か冷凍で保存し、湿気や結露を避けることが大切です。
使い切りやすい個包装タイプを選ぶと管理がラクになります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3e3aeeeb.6cad7359.3e3aeeed.7f7fd17c/?me_id=1412398&item_id=10000001&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftomizawa-2%2Fcabinet%2Fitem01%2F02135307_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/285762a9.762a8dc9.285762aa.474c8b2b/?me_id=1194096&item_id=10002249&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmamapan%2Fcabinet%2Fyeast%2F12000041.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49019c0f.584dd1bc.49019c10.6a2c5999/?me_id=1417207&item_id=10000481&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmk-mart2%2Fcabinet%2Fimgrc0128747198.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49019c0f.584dd1bc.49019c10.6a2c5999/?me_id=1417207&item_id=10000482&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmk-mart2%2Fcabinet%2Fimgrc0126544436.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/32ac9d08.5521958a.32ac9d09.df0b88f6/?me_id=1243719&item_id=10000631&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fboulan-%2Fcabinet%2F00901040%2Fimgrc0105919867.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d149854.adcefb22.1d149855.aebb13f5/?me_id=1261122&item_id=10844032&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F459%2F35459.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49019c0f.584dd1bc.49019c10.6a2c5999/?me_id=1417207&item_id=10000556&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmk-mart2%2Fcabinet%2Fimgrc0132518258.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)







