
こんにちは、現役パン教室講師/教室運営コンサルタントのyuiko です。
イースト臭が苦手という自分の体質から、微量イースト&国産小麦を使ったオーバーナイト製法のパン作りにたどり着きました。
現在は、素材の良さを活かしたパン作りを伝えるオーバーナイト専門のパン教室を主宰しています。
また、cottaパートナーとしても活動中。
パン作りに慣れていないと、「二次発酵って本当に必要?」と思うこともありますよね。
けれどこの工程を飛ばすと、仕上がりがまったく変わってきます。
二次発酵をしないまま焼くと、パンがふくらまず、表面が割れたり、かたくなる原因に。
せっかくこねて発酵させたのに、最後の仕上げを抜いてしまってはもったいないです。
二次発酵は、ふわっとした食感に仕上げるための大事な時間。
生地の中のガスをきれいに整えて、オーブンでうまく膨らむように準備する工程です。
特別な技術は必要ありませんが、焦らず“待つ”ことがポイント。
時間をかけたぶん、パンのおいしさにしっかり表れてくれます。
パン作りで二次発酵しないとどうなる?


二次発酵は、焼く直前の生地に“最後のふくらみ”を与える大切な工程です。
一次発酵でガスが発生したあと、生地を成形して、再びふくらませる時間がこのステップ。
ここを飛ばしてすぐに焼くと、膨らまず、表面が割れたり、食感が固くなる原因になります。
とくに初心者がやりがちなのが「一次発酵で膨らんだから大丈夫」と思い込むこと。
それでは、まだ完成とは言えません。
二次発酵は、ふわっと軽い食感ときれいな焼き上がりに欠かせない重要な工程です。
この時間をしっかり取ることで、クープも自然に開き、火の通りも均一になります。
「焼くだけなのに、なんだかうまくいかない」
その違和感は、二次発酵の不足が原因かもしれません。
発酵しないで焼くとパンが膨らまない・硬くなる
二次発酵をしないまま焼くと、パンが膨らまず、かたくなってしまうことが多いです。
見た目も平べったく、ふんわり感が出ません。
パンは、焼く前の生地がふわっとふくらんでいることが大切。
そのために必要なのが、焼く直前の二次発酵です。
発酵が足りないと、オーブンに入れても中から持ち上がる力が弱いため、うまくふくらまず、かたい食感に。
初心者のうちは「もういいかな?」と早めに焼いてしまいがちですが、指で生地を軽く押して、ゆっくり戻るようならOK。
これが二次発酵の完了サインです。
待つことも、パン作りの大事なスキル。
時間をかける価値、あります。
生地のキメが粗くなり口当たりが悪くなる
二次発酵が足りないと、パンの中の気泡が不ぞろいになります。
その結果、キメが粗くなり、食べたときにパサついた食感になってしまいます。
理想は、ふわふわ・しっとり。
そのためには、二次発酵の時間で生地の中の空気を整えることが大事です。
焼きたてのパンをカットしたときに、断面がぼそぼそしていたら要注意。
それは、二次発酵が不十分だったサインかもしれません。
「食感がいまいち」「口に残る感じがする」と感じたら、次回はもう少し発酵時間をとってみましょう。
パンは少しの違いで大きく変わります。
焼成時にクープが開かない・表面が割れる
パンに切り込み(クープ)を入れてもうまく開かない。
それは、二次発酵が足りないからかもしれません。
発酵がしっかりできていないと、生地がまだかたくて、オーブンでうまく膨らまず、切り込みも開かないのです。
また、クープを入れなかったところから無理に膨らもうとして、パンの表面がボコっと割れてしまうことも。
きれいに焼きたいなら、クープが自然に開くくらい、生地をやわらかくふくらませておくことがポイントです。
パンの仕上がりは、見た目も大切。
丁寧に発酵させておくことで、見た目にも美しいパンが焼けます。
中まで火が通りにくく焼きムラが出やすい
パンの外側は焼けているのに、中が生っぽい。
そんなときは、生地がふくらまずに詰まっていたことが原因かもしれません。
発酵が足りずに焼くと、中がぎゅっと詰まって熱が通りにくくなります。
とくに大きめのパンや食パンは、中までしっかり焼くにはふんわりした生地が必要です。
二次発酵で生地がふくらんでいると、オーブンの熱が入りやすくなり、均一に焼き上がります。
ムラなく焼くためにも、焼く前の生地の状態はとても重要です。
「焼きムラが多い」と感じたら、次はもう少し発酵時間を長くしてみるとよいかもしれません。
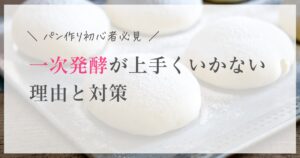
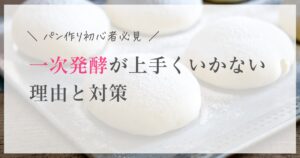
パンが二次発酵で膨らまない時の5つの対処法


「思ったよりふくらまない…」
そんなとき、あわてて焼いてしまうのはNGです。
パン生地が二次発酵でふくらまないのには、必ず原因があります。
ちょっとした温度のズレ、イーストの状態、生地の扱い方。
見直せるポイントはいくつもあります。
慣れないうちは、「失敗かも」と決めつけず、原因を1つずつ確認してみることが大切です。
ここでは、初心者でもすぐにチェックできる5つの対処法をご紹介します。
どれも専門知識がなくてもできる内容です。
あきらめる前に、試してみてください。
①発酵温度と湿度を見直す
パン生地は温度と湿度にとても敏感です。
寒すぎたり、空気が乾燥していると、うまくふくらまない原因になります。
発酵機能があるオーブンや、レンジの発酵モードを使うと簡単に調整できます。
なければ、コップ1杯の熱湯を入れた密閉容器に生地を置くだけでも◎。
また、乾燥を防ぐためにラップやぬれ布巾をかけるのも大事なポイント。
発酵が進まないときは、まず環境の見直しから始めてみましょう。
②時間を延ばして様子を見る
ふくらみが足りないと感じたとき、「もうダメかも」と思わずに、まずは少し時間を足してみましょう。
特に冬場や湿度の低い日は、発酵に時間がかかることがあります。
レシピに「40分」と書いてあっても、その通りにふくらむとは限りません。
発酵は「時間」ではなく「生地の状態」で見るのが基本です。
指で軽く押して、ゆっくり戻るようなら発酵完了のサイン。
10〜15分延ばすだけでふわっと膨らむこともよくあります。
「もう少し待ってみる」
そんな判断ができると、パン作りの精度がグッと上がります。
③発酵が止まっていたらイーストが死んでいる可能性も
温度も湿度も問題ないのにまったく膨らまない。
そんなときは、イーストが働いていないかもしれません。
イーストは熱や時間に弱い生き物のような存在。
60℃以上の熱湯に直接入れると、すぐに死んでしまいます。
また、古くなったり、空気に触れて劣化したイーストも発酵力が落ちてしまいます。
使う前に予備発酵(ぬるま湯+砂糖に溶かして泡立つかチェック)してみると安心です。
泡が出なければ、新しいイーストを用意しましょう。
発酵しないとき、生地ではなく“イースト自体”に原因があることもあるのです。
④成形時にガスを抜きすぎていないか確認
パンの成形時、つい力を入れて生地を押してしまうことはありませんか?
このとき、中のガスを全部抜いてしまうと、二次発酵でふくらみにくくなります。
ガスを抜くのは大事ですが、完全に抜ききってしまうのはNG。
一次発酵でできた細かい気泡をほどよく残すことで、次のふくらみにつながります。
コツは、生地をやさしく扱うこと。
ベンチタイムで少し休ませてから、力を入れすぎずに丸めるだけでOKです。
ガスを押し出すというより、形を整えるイメージで。
ふんわり感を出すには、手加減がとても大切です。
⑤一次発酵の取りすぎでイーストが力尽きていないか見直す
一次発酵に時間をかけすぎると、イーストがそこで力を使い果たしてしまうことがあります。
そうなると、二次発酵で膨らむ力が残っていません。
とくに夏場は、生地の温度も上がりやすく、思った以上に発酵が進みやすい時期。
気づいたら過発酵になっていた…というのは、よくある失敗です。
一次発酵の目安は「生地が2倍の大きさになるまで」。
押してみて、指の跡がそのまま残るくらいがちょうどよいタイミングです。
「念のためもう少し」は禁物。
発酵もやりすぎると逆効果になることを覚えておきましょう。


パンの二次発酵を常温で行う方法と発酵時間


パン作りに慣れていないと、「発酵器がないと無理かも」と思いがちですが、実は常温でもじゅうぶん発酵は可能です。
特別な道具がなくても、温度と湿度に気をつければ、ふっくら仕上げることができます。
ただし、季節や室温によって発酵のスピードが変わるため、時間ではなく“生地の状態”をしっかり見ることが大切。
常温発酵のコツは、「環境を整えること」と「焦らないこと」。
この章では、パンの二次発酵を自宅で無理なく行う方法を解説します。
初心者でも実践できるポイントばかりなので、発酵器がなくても安心してください。
常温発酵に適した室温は25〜28℃が目安
二次発酵を常温で行うときは、室温が25〜28℃程度あるとちょうどよい環境です。
この温度帯は、イーストが活動しやすく、ゆっくり安定して発酵が進むと言われています。
夏場は自然にこの温度になることが多く、特別な工夫はいりません。
一方で、冬や冷房の効いた部屋では、室温が足りないことがあるので注意が必要です。
温度が低いと発酵が進まず、いつまで経ってもふくらまない原因に。
逆に高すぎると、イーストが元気を失ったり、生地が乾燥してしまうことも。
「今の室温ってどうなんだろう?」と思ったら、室内用の温度計をひとつ用意しておくと便利。
発酵は「環境次第」で大きく変わる、繊細な工程です。
乾燥を防ぐためにラップや濡れ布巾で覆う
常温発酵では、生地の乾燥を防ぐことがとても重要です。
生地の表面が乾いてしまうと、硬くなって膨らみにくくなり、焼いたときに割れやすくなります。
対策としては、生地をボウルやバットに入れて、上からラップをふんわりかけるのが基本。
ラップの代わりにぬらした布巾を軽くかけてもOKです。
ただし、ぬれ布巾の場合は乾いてしまいやすいため、途中で一度水を含ませ直すことも大切。
また、できるだけ風の当たらない場所に置くことも乾燥対策になります。
換気扇の近くやエアコンの風が当たる場所は避けましょう。
表面の状態ひとつで、焼き上がりの美しさや食感が変わります。
小さなことですが、しっかり対策しておきたいポイントです。
発酵の見極めは時間ではなく「状態」で判断
見極めの目安は、生地を指でそっと押してみること。
軽く押して、ゆっくりと戻る、または指の跡が少し残るくらいならOK。
逆に、すぐに戻る場合は発酵不足。
押したあとがベタッと沈んだままなら過発酵の可能性があります。
発酵を見極める力は、回数を重ねることで自然と身についていきます。
「今日は少し膨らみが遅いな」と感じたら、時間よりも生地の表情を見てあげてください。
発酵器なしでも安定させるには?
発酵器がなくても、ちょっとした工夫で家庭でも安定した発酵環境はつくれます。
たとえば
- オーブンの発酵モード(30℃前後)があれば活用する
- 電子レンジに生地を入れ、コップ1杯の熱湯を一緒に置く
- 保温ボックスや発泡スチロールに入れて温度を保つ
これらの方法なら、特別な道具がなくても温度と湿度を確保することができます。
また、発酵中に移動させると温度が下がることがあるので、できるだけ動かさずに置いておくのがポイント。
発酵は難しそうに見えて、環境を整えれば誰でも成功できます。
安心して、まずは手元にあるもので始めてみてください。
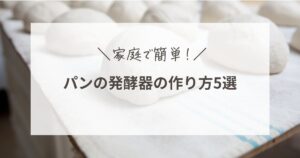
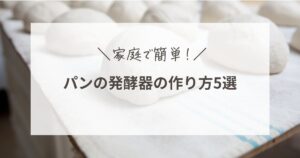
パンは二次発酵後すぐ焼かないとどうなる?


パン作りの中でも、「焼くタイミング」はとても重要なポイントです。
とくに二次発酵が終わったあとの生地は、時間との勝負。
この状態で放置してしまうと、せっかくふっくら膨らんだ生地がしぼんだり、表面が乾いて食感に悪影響が出てしまいます。
でも、どうしてもすぐ焼けないときもありますよね。
そんなときは、生地を守る工夫を知っておくことで、失敗を防げます。
ここでは、二次発酵後にすぐ焼かないとどうなるのか、そして対処法やリカバリーの方法までくわしく解説します。
初心者でも今日から実践できる内容です。
時間が経つと過発酵になり生地がダレる
二次発酵が終わったパン生地をそのまま放置しておくと、イーストが発酵しすぎて過発酵になります。
その結果、生地のハリがなくなり、だらんと広がってしまうのです。
過発酵になると、焼いてもふくらまず、食感もスカスカに。
見た目も悪くなり、表面がしわしわになることもあります。
「ふくらんでるから大丈夫」と思っても、ふくらみすぎは逆効果。
一度限界を越えると、生地は元に戻りません。
二次発酵が終わったら、時間をあけずに焼くのが基本。
どうしても時間が取れないときは、冷蔵庫に入れて発酵を遅らせるなどの工夫が必要です。
ガスが抜けてボリュームが出なくなる
発酵が終わった生地を放置すると、中にたまったガスが抜けてしまうことがあります。
このガスこそが、焼いたときにパンをふくらませてくれる力です。
ガスが抜けてしまうと、オーブンに入れても生地が持ち上がらず、ぺたんこな焼き上がりに。
パンの中に気泡ができず、食感も詰まったようになります。
また、ガスが抜けることで、生地の構造も弱くなり、焼成時に形が崩れたり、クープが開かなくなることもあります。
二次発酵後は、ふくらんだタイミングを逃さないようにすることが大切。
生地のピークを見極めて、できるだけすぐに焼く習慣をつけましょう。
表面が乾燥して焼き色や食感に悪影響が出る
さらに、表面が乾いてしまうと、オーブンの中でうまく膨らまず、クープも開きにくくなります。
焼き上がりの見た目がゴツゴツしてしまったり、焦げやすくなることも。
これを防ぐためには、発酵後もラップや布巾をかけておくことが基本。
乾燥はほんの10〜15分でも進んでしまうので、油断は禁物です。
焼くまでの数分間も、生地を守る意識を持っておくと、仕上がりがぐっと良くなります。
すぐ焼かない時は冷蔵庫で遅延発酵がおすすめ
「今すぐ焼けない」「あと30分だけ待ちたい」
そんなときにおすすめなのが、冷蔵庫での遅延発酵です。
冷蔵庫に入れることで、イーストの働きを一時的に弱め、発酵の進行をゆるやかにすることができます。
これなら、過発酵になるのを防ぎながら、焼きたいタイミングまで生地をキープできます。
注意点は、乾燥しないようにしっかり密閉すること。
ラップ+ビニール袋、または密閉容器に入れると安心です。
焼く前には、常温に戻してからオーブンへ。(ただし、この間も発酵は進むので注意!)
時間が空いてしまうときは、この方法で生地のベストな状態を保ちましょう。
リカバリーするなら軽く丸め直して再発酵
「うっかり時間が経ってしまった…」
そんなときでも、あきらめるのは早いです。
生地の状態によっては、軽く丸め直して再発酵することでリカバリーできる場合もあります。
やり方は、手に粉をつけて生地をやさしく丸め直すだけ。
中のガスを少し抜いて、生地をリセットします。
その後、15〜20分ほど再び発酵させてから焼けばOK。
ただし、すでにベタついていたり、生地がだれている状態だと、再発酵ではうまく戻らないこともあります。
あくまで応急処置ですが、失敗をゼロにせず、“活かす”方法を知っておくと安心です。
パン作りに「完璧」はありません。
対応できる柔軟さこそ、上達の近道です。


パンの二次発酵をオーブンでやる場合の正しい手順と注意点
パン作り初心者でも扱いやすいのが、オーブンの発酵機能を使った方法。
温度や湿度の管理がしやすく、ふくらみの失敗が少ないのが特徴です。
ただし、使い方を間違えると、乾燥や過発酵の原因になることもあります。
大切なのは、適切な温度設定・湿度対策・タイミングの管理。
発酵モードがついていないオーブンでも、工夫すれば同じように発酵環境をつくれます。
自分のキッチンに合った方法を見つけて、パン作りをもっと気楽に。
ここでは、オーブンで二次発酵を行うときの正しいやり方と、注意しておきたいポイントをまとめました。
オーブンの発酵モードは35℃前後に設定する
40℃以上になると、イーストが弱ってしまうおそれがあります。
逆に30℃以下では、発酵がゆっくりすぎて膨らみにくくなることも。
設定温度がない場合は、「発酵」「あたため」などの低温モードが代用可能。
それでも不安なときは、庫内に温度計を入れて確認すると安心です。
オーブン発酵のメリットは、安定した温度環境で失敗が少ないこと。
まずは温度の設定から整えてみましょう。
発酵機能がない場合は湯せんで代用できる
オーブンに発酵モードがついていなくても、工夫次第でしっかり発酵させることができます。
おすすめは、お湯を使った“湯せん発酵”。
方法はとても簡単です。
大きめの容器(耐熱バットやボウル)に40〜50℃のお湯をはり、その上に網などを置いてパン生地を乗せるだけ。
生地が直接お湯に触れないように注意しながら、庫内に入れてドアを閉めれば簡易発酵室の完成。
これなら、発酵モードのないオーブンでも温度と湿度をしっかり確保できます。
手軽にできて効果的なので、初心者にもおすすめの方法です。
発酵中はスチームで乾燥を防ぐ
オーブンで発酵させると、庫内が乾燥しやすいというデメリットがあります。
生地の表面が乾いてしまうと、ハリがなくなったり、焼き上がりに影響が出ることも。
対策として、スチームを使って湿度を保つことが大切です。
スチーム機能がない場合でも、カップに熱湯を入れて庫内に一緒に置くだけでOK。
また、生地にはラップやぬれ布巾を軽くかけておくと、より乾燥を防ぎやすくなります。
ポイントは、ふんわりと覆って、ふくらむスペースを残すこと。
たったひと手間で、ふわっとしたやさしい焼き上がりにつながります。
発酵後すぐ焼けるよう、予熱タイミングを事前に決める
発酵が終わったあとは、できるだけ早く焼くのが鉄則です。
でも、オーブンの予熱が間に合っていないと、生地が待っている間に過発酵に。
これを防ぐためには、予熱のタイミングを事前に逆算しておくことが大切です。
たとえば、「あと10分で発酵が終わりそう」と感じたら、その時点で予熱をスタート。
生地のふくらみ具合を見ながら、「焼き始めたいタイミングから逆算して予熱」が理想です。
オーブンによっては予熱に10〜15分かかることもあります。
待たせずにスムーズに焼けるように、段取りも意識しておくと、失敗がぐんと減ります。
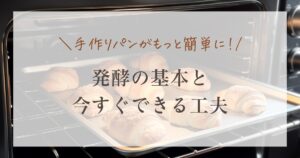
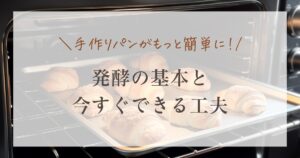
よくある質問(FAQ)


パン作りに慣れていないと、発酵の温度やタイミングで迷うことは多いもの。
特に二次発酵は、「どのくらいの温度がいいの?」「失敗したらどうすればいいの?」と悩みがちです。
ここでは、よく聞かれる疑問に初心者向けにやさしくお答えします。
迷ったときにすぐ確認できるよう、シンプルにまとめました。
まとめ|パンの二次発酵は「待つ力」が仕上がりを変える
パン作りで二次発酵をおろそかにすると、ふくらまない・固い・焼き色が悪いなど、あらゆる失敗につながります。
一方で、温度や湿度を整え、発酵の状態をしっかり見極められるようになると、見た目も食感もぐんとレベルアップ。
今回の記事でお伝えしたポイントは次の通りです:
- 二次発酵はパンの完成度を左右する工程
- 膨らまないときは温度・湿度・イーストを確認
- 常温・オーブン・冷蔵庫でも正しく行えばOK
- 発酵後は時間を空けずに焼くのが鉄則
- 失敗してもリカバリーの方法はある
パン作りに慣れていないうちは、戸惑う場面もあるかもしれません。
でも、大切なのは“待つ勇気”と“小さな違和感に気づく目”。
一歩ずつ経験を重ねて、理想のふわふわパンを目指していきましょう。








